どーもこんにちは!今回は【歌ってみた】の作成には確定で必須のピッチ補正について語っていきます。
まず、
ボーカルのピッチ(音程)やタイミングを修正する作業をボーカルエディットといいます。
ボーカルエディット→MIX作業(ミキシング)の順番で作業しましょう
エディット作業は、大きく分けると
- 録音テイクの中から良い部分を組み合わせてベストテイクを作り、
- ピッチやタイミングを補正し、
- 録音中に入ってしまったノイズの除去する、
ピッチ補正のプラグインはどこの使えばいい?
ピッチ補正プラグインには無料版と有料版がありますが、無料版では「VocalShifterLE」や、「KeroVee」が有名です。
「VocalShifterLE」は「VocalShifter」という有料ソフトの無料版なのですが、有料版に比べて対応している音質が低くなっています。
正直僕はこれ使いにくく音質も変わりすぎているので大きな音程の変化をしなければならないときは役にたたなかったです。
ピッチ補正のやり方を学びたい方にはおすすめです。
無料でピッチ補正をする方法 VocalShifterを使ってピッチ補正をしよう – たかじんブログ (takazin-blog.com)
また「KeroVee」はその名の通りケロケロボイスを作ることに特化していることで有名ですが、最近では自然な補正にも力を入れてきているそうです。
またvstとして機能し、操作が非常に簡単なため、とりあえずピッチ補正をしてみたい人におすすめです。
有料版ソフトではCelemony社の「Melodyne」シリーズや、Antares社の「Auto-Tune」、Waves社の「Waves Tune」シリーズがおすすめです。
またSteinberg社のDAWである「Cubase」シリーズには「Vari Audio」というピッチ補正ソフトが付属しているのでCubaseを使用している方はこれを使ってみましょう。
有料版の↑たちはどれも良いです。間違いありません。ちなみに僕はMelodyneを使っています。
ベストテイクを録り、カット&ペースト
4~5テイク録っても駄目な場合は何テイク録っても駄目です(笑)また、日をまたぐと歌い方や歌のテンションが変わってしまうこともあるため、できることなら1日のうちに全て録り終えてしまいましょう。
万が一、日をまたぐ場合は前回に録音した音源を聴きながら歌い方を合わせてつなぎ目が不自然にならないように気を配ります。
全体的にいい感じで録り終えたら、録音したテイクの中から特に良い部分を組み合わせて1つのベストテイクを作ります。
これは編集する人にもよりますが、ブレスごとに継ぎ接ぎしていく場合が多いです。こだわる場合は1音1音選んでいくこともありますが、音と音のつなぎ目が不自然になることが多いので慎重に作業を進めていきます。
正直に言いますと、この作業がボーカルに関する作業の中で一番重要になってきます。
良いテイクができないと、いくらピッチ補正やミキシングを頑張ったところでどうにもならないことが多いです。![]()
ピッチ補正のやり方
**説明に使用しているのはMelodyneです**
ソフト内部にファイルを転送しよう
まずは大体のピッチ補正ソフトはソフト内部にボーカルを録音したものを編集する形式をとっていますので、ソフト内に編集するボーカル音源を録音します。
Melodyneでは左上の「転送する」というボタンを押してからトラックを再生することで録音することができます。
このときは別に他のトラックが鳴っていてもソフトの録音には支障がないのでカラオケ音源と一緒に流しながらどこを修正するのかチェックをしていくと後の作業を効率的に進めることができます。
まずはピッチだけを編集しよう
本来は耳で判断して音程を変えていくのですが、 (音程なんて分かんないよー―)って人は、、(○○←曲名 ピアノ簡単)とYouTubeで検索すると、楽譜が読めない人用に存在する動画があるのでそれを参考にしてピッチ補正していきましょう。
完璧に本家の音程通りだと機械みたいに聴こえてしまうので人間らしさが無くなるくらい変えるのはやめましょう。
ここでは最初にピッチを直していくことにします。慣れたらピッチとタイミングを並行して直すことも可能になりますが、初めての場合はピッチのときはピッチだけに注目して修正をかけていったほうがやりやすいです。
まずは全体のピッチを40%~70%程度で直します。
100%にしないのは完璧に直された音源を聴いてしまうとそれに慣れてボーカルの個性を消してしまう編集をしてしまう可能性が高くなるためです。
そしてチェックした、特に気になる箇所のピッチが高いのか低いのかを判断しながら直していきます。
たまに修正したい箇所を直していたらその前後の音まで動いてしまう場合があります。
そういうときには「はさみツール」などを用いて前後の音と切り離すことで個別に編集することができるようになります。
また、ロングトーン(長く伸ばす音)などで音の真ん中は丁度良いんだけど、出だしがズレている場合などは、ピッチの揺れを修正する機能を使います。
Melodyneでは「ピッチドリフトツール」、「ピッチモジュレーションツール」と呼ばれています。
完結にいいますと前者はしゃくりやフォールなどの音のブレを変える機能、後者がビブラートの強さを変える機能です。
Melodyne以外のプラグインにも似た機能が搭載されていますので、これらの機能を使って修正していきます。
ここでもやりすぎると人間味を失ってしまうので気をつけましょう。
逆にこれらの機能を使い、音の揺れをなくすことでケロケロボイスを作ることもできます。
また先程の「はさみツール」などを使ってロングトーンの一部だけを編集することもできます。![]()
タイミングを修正しましょう
次にタイミングを修正していきます。まずはピッチと同様に全体の40%~70%程度で直します。
そしてチェックした箇所を直していくのですが、ここで注意点が2つあります。
1つ目が、一つの音のタイミングを編集するとその前後の音にも影響がある場合があるということです。
全体の長さを変えずに繋がった2つの音の片方の長さを長くするためにはもう片方を短くするか、休符を増やさなければいけません。
やりすぎると歌の印象が変わりすぎたり、不自然になったりしてしまうので注意しましょう。
2つ目はリズムをクリックではなくカラオケ音源に合わせるということです。
最近の音楽は打ち込み技術の発展によって機械が演奏していることが多くなってきましたが、実際に打ち込んでいるのは人間なのでクリックに対して多少のズレがあったり、あるいは人間的な心地よい演奏にするために意図的にリズムをズラしてたりしている場合があります。
また生演奏のカラオケ音源の場合にはそれが顕著になっていることもあったりしますね。
実際に音源にするときにはクリックは鳴っていないので、カラオケ音源にタイミングを合わせるようにします。
具体的な編集方法はピッチのときと似ており、気になった箇所を個別で一つ一つ編集していきます。
前後が繋がってしまっているときには同様に「はさみツール」を使います。
また音量によっても歌のノリが変わることがありますので、場合によっては音量ツール等を使い自然に聴こえるように修正していきましょう。
これらの編集作業では聴けば聴くほど色々なところが気になって来て、ついつい修正しすぎてしまうことがありますので、分からなくなってきたら参考となる音源を聴いたり、何か他のことをして気分を変えたりすることもオススメです。
おしまい
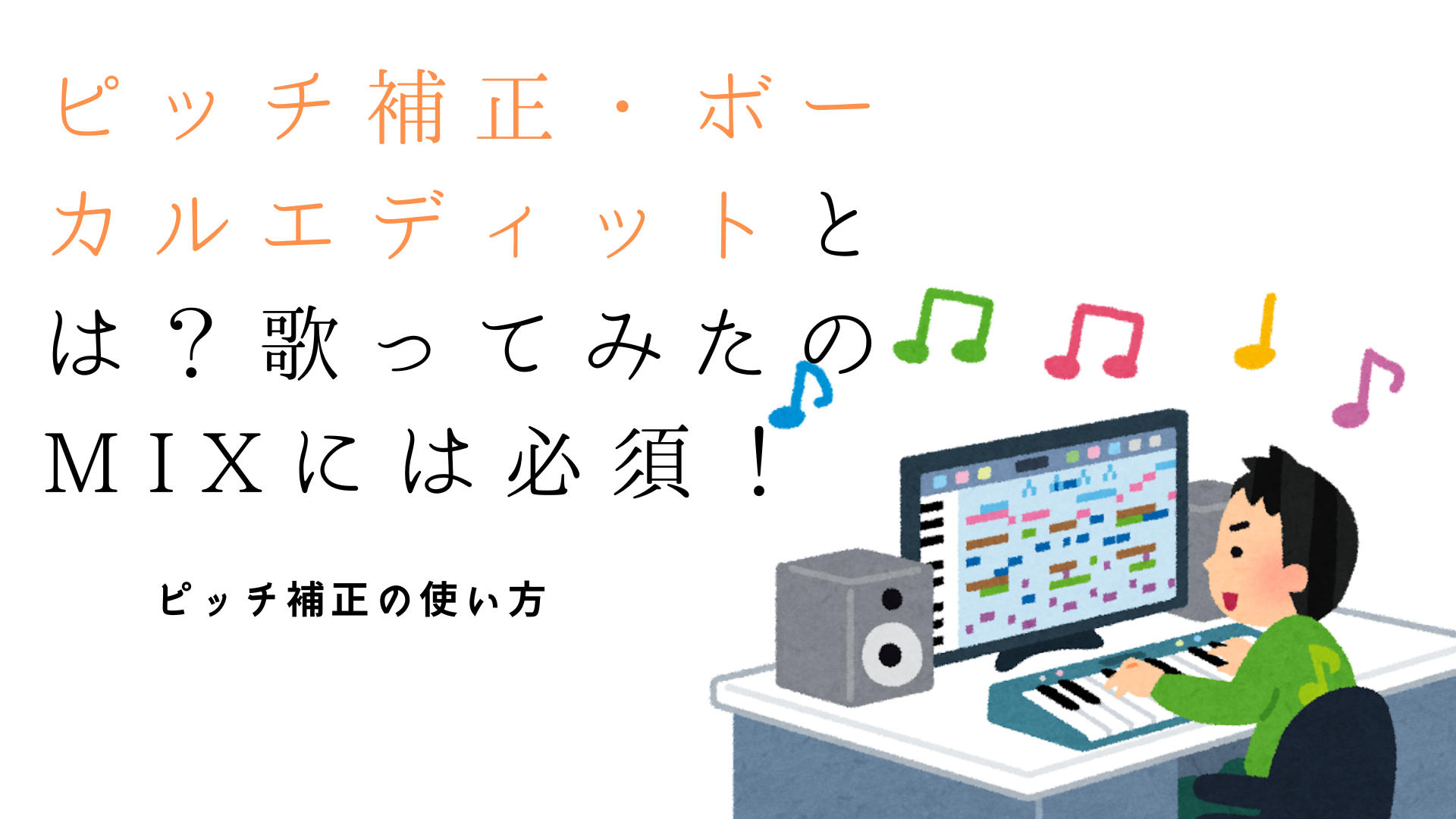


コメント